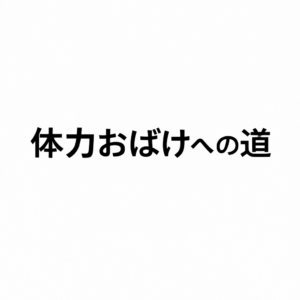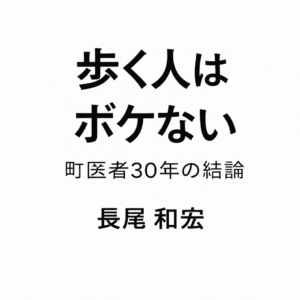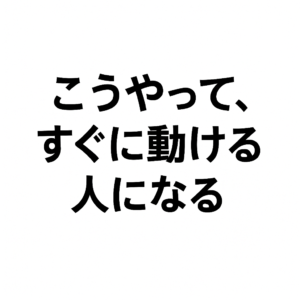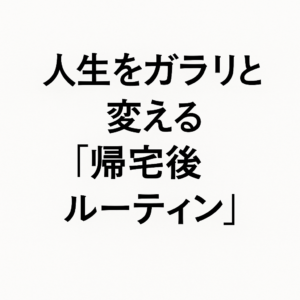「心が不安定なのは性格じゃない」——『気分の9割は血糖値』が教えてくれる、食事と心の意外な関係
最近、なんとなくイライラしたり、やる気が出なかったりしませんか?
仕事のストレスや人間関係のせいだと思いがちですが、実はその不調、血糖値が関係しているかもしれません。
小池雅美さんの『気分の9割は血糖値 食事 健康』は、「心のコンディションは食事で変わる」という視点から、メンタルケアと栄養学をやさしくつなぐ一冊です。読み進めるうちに、自分の気分が“体の反応”によって左右されていたことに驚かされます。
■ 血糖値の波が「気分の波」をつくる
本書の軸となるのは、「血糖値の急上昇と急降下が、気分の不安定さを生む」というシンプルな考え方。
私たちはつい、落ち込んだりイライラしたりするのを“心の弱さ”と捉えがちです。でも小池さんは、それが「血糖値スパイク」と呼ばれる現象によるものだと指摘します。
たとえば、朝に菓子パンや甘いカフェラテを摂ると、血糖値は一気に上がり、すぐに下がります。その結果、脳が「エネルギー不足」と勘違いし、集中力が切れたり、怒りっぽくなったりする。
つまり、食事の内容がそのまま気分の安定に影響しているというわけです。
『気分の9割は血糖値 食事 健康』では、この仕組みを誰にでもわかる言葉で説明しながら、すぐに実践できる食生活のヒントを紹介しています。
■ 「心を整える食事」は、特別なことではない
多くの人が「健康的な食事」と聞くと、難しそうに感じるかもしれません。
でも、小池さんの提案はとてもシンプルです。
たとえば──
- 朝食にタンパク質(卵・納豆・ヨーグルト)を取り入れる
- 食事の最初に野菜を食べる
- 甘いものを食べるなら「食後」に
- カフェインを摂るタイミングを工夫する
どれも今日からできることばかり。
それでいて、気分のムラが減り、1日を通してエネルギーが安定するというのだから驚きです。
『気分の9割は血糖値 食事 健康』は、難しい理論よりも「体の声を聞く」ことを大切にしています。食べ方を変えるだけで、心まで穏やかになる——その実感が、読者の心を軽くしてくれます。
■ この本から得られる4つの気づき
読後に特に印象に残るのは、「心と体のバランスは、日々の“選択”で整えられる」というメッセージです。
ポイントを整理すると、次の4点が際立ちます。
- 食事は“栄養”だけでなく、“感情”にも影響する
- 健康的なリズムは、朝の一口から始まる
- 我慢ではなく、“バランス”を意識する
- 「ちゃんと食べること」が、最高のメンタルケア
この考え方は、ダイエットや栄養指導の枠を超えて、「自分を大切にする習慣」にまでつながります。食事と健康を切り離さない視点が、心の安定を生むというのです。
■ よくある質問に答えます
Q:食事を変えるだけで本当にメンタルが変わるの?
A:はい。『気分の9割は血糖値 食事 健康』では、食事内容が血糖値を通じて脳内ホルモンや自律神経に影響を与えることを科学的に説明しています。実際、食事を整えたことで「イライラが減った」という実例も多数紹介されています。
Q:忙しくてもできる?
A:できます。外食やコンビニ食でも“選び方”を意識すれば大丈夫です。例えば「パンよりおにぎり」「甘い飲料より水やお茶」といった小さな工夫が鍵になります。
Q:ダイエット本とは違うの?
A:違います。『気分の9割は血糖値 食事 健康』は、体重ではなく“気分”に焦点を当てた本。減量よりも「心の安定」を目的としています。
■ まとめ:食べ方を変えれば、人生が穏やかになる
- 血糖値の乱れは、気分の乱れに直結する
- 小さな食習慣の改善が、心の安定をもたらす
- 「健康」と「幸福感」は、実は同じ場所から生まれる
『気分の9割は血糖値 食事 健康』は、忙しい現代人にこそ読んでほしい“心の栄養学”。
心の不調を「自分のせい」と思わずに、「食べ方を見直してみよう」と優しく教えてくれる本です。
今、疲れを感じているあなたへ——食事が、いちばん身近なセラピーになるかもしれません。
詳しくはこちら→https://amzn.to/4hxJow8