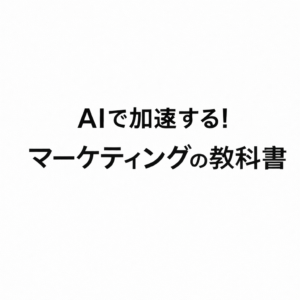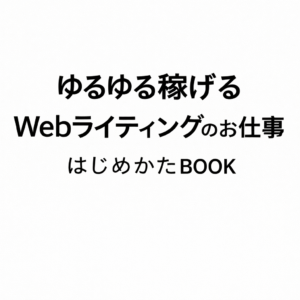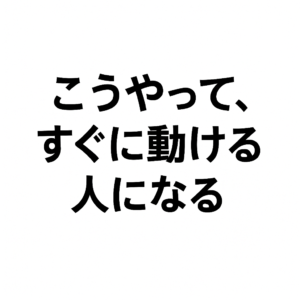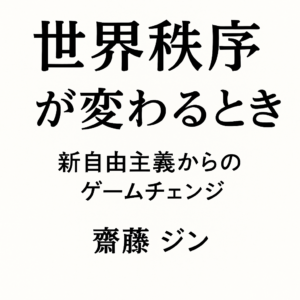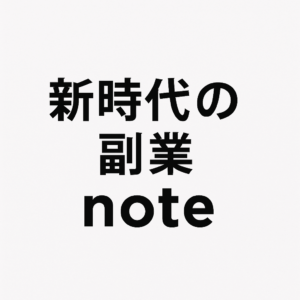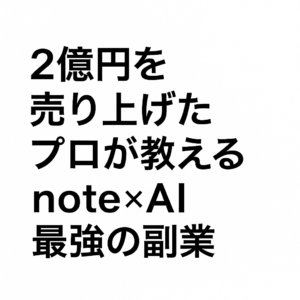ビジネスの現場では「話し方」よりも「話す前にどう考えるか」が成果を大きく左右します。
安達裕哉氏のベストセラー『頭のいい人が話す前に考えていること』は、2025年も多くのビジネスパーソンに読まれている一冊です。
本記事では、本書の要点を 7つのポイント に整理し、プレゼン・会議・日常会話にすぐ活かせる実践的な内容をまとめました。
「伝える力を磨きたい」「仕事の成果を上げたい」という方はぜひ参考にしてください。
『頭のいい人が話す前に考えていること』要点まとめ
1. 話す前に「相手の視点」を想像する
相手の立場に立ち、必要な情報を優先して伝えることが重要です。
自分中心の話し方は相手に響かず、誤解や不信感を招きやすくなります。
例えば会議で提案をする際、自分が伝えたいことではなく「相手が判断するために必要な情報」を先に提示すると、より効果的に理解してもらえます。
相手視点を持つことで、信頼される話し方につながります。
2. 事実・解釈・感情を分けて考える
「事実」「解釈」「感情」を切り分けることで、論理的に伝えられるようになります。
情報が混ざると相手は混乱しやすく、正しく理解できません。
例えば「売上が下がった(事実)」「景気が悪いからだ(解釈)」「不安だ(感情)」を整理して伝えることで、筋の通った説明になります。
主観と客観を分けることは、説得力を高める大切な技術です。
3. 短く、具体的に話す習慣を持つ
長い説明よりも、短く具体的な言葉のほうが相手に伝わります。
相手はすべてを記憶できないため、要点がぼやけやすいのです。
例えば「資料作成をお願いします」よりも「明日17時までに5ページの資料を作成してください」と依頼する方が的確です。
具体的で端的な表現が、理解と行動を促します。
4. 問いを立ててから答える
話す前に「問い」を立て、その答えを伝えると論理が整理されます。
問いがあることで話の目的や方向性が明確になり、相手も理解しやすくなります。
例えば「なぜ売上が下がったのか?」という問いを立て、「新規顧客数が減ったからです」と答えると、筋の通った説明になります。
問いを活用することで、分かりやすい会話を実現できます。
5. ゴールから逆算して言葉を選ぶ
最終的に相手にどう行動してほしいかを基準に話すことが大切です。
目的を意識せずに話すと、情報が散漫になり、行動につながりません。
例えば契約を取りたいプレゼンでは、細かい背景説明よりも「導入後のメリット」を優先して伝えるべきです。
ゴールを基点に話すことで、成果に直結する会話ができます。
6. 相手の前提知識を推定する
相手の知識レベルに応じて言葉を調整することが求められます。
専門用語や抽象的な表現は、相手の理解度によっては伝わらない可能性があるからです。
例えば専門家には「ROI」で通じますが、初心者には「投資に対して得られる利益」と説明するほうが分かりやすいでしょう。
相手の理解度を推測し、言葉を選ぶことが信頼を築く鍵です。
7. 聞き手の時間を大切にする意識
相手の時間を奪わない簡潔な話し方を意識することが大切です。
回りくどい説明は相手にストレスを与え、信頼を損なう原因になります。
例えば会議の冒頭で「今日は3点だけお伝えします」と伝えると、相手は安心して話を聞けます。
時間を尊重した伝え方は、効率的で信頼されるコミュニケーションにつながります。
まとめ
『頭のいい人が話す前に考えていること』は、話し方そのものではなく「話す前の思考整理」こそが伝える力の核心であることを教えてくれます。
2025年のビジネス環境でも「伝わる人」と「伝わらない人」の差は大きく、この本を読むことでその差を埋めるヒントを得られるでしょう。
プレゼン・会議・日常会話など、あらゆる場面で活かせる内容なので、自己成長を目指す方に強くおすすめできる一冊です。