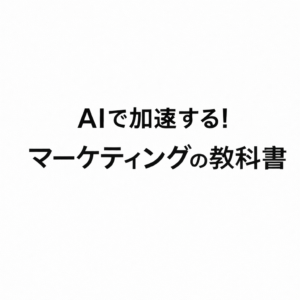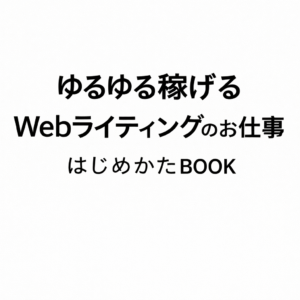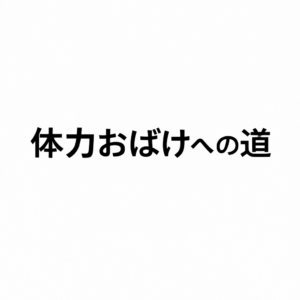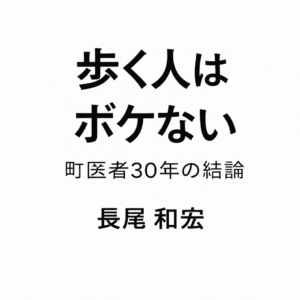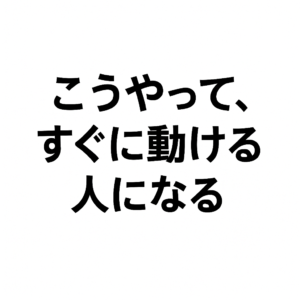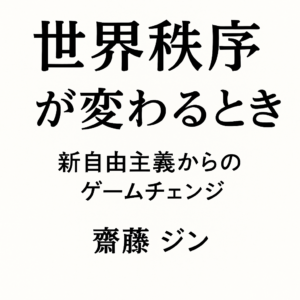「努力すれば報われる」は本当か?——『移動と階級』が突きつける、現代日本の“見えない壁”
「チャンスは平等」と言われるけれど、本当にそうだろうか。
どれだけ努力しても、報われない人がいる。
そして、一部の人だけが安定と成功を手にしている——。
伊藤将人さんの『移動と階級 』は、そんな現代社会の“静かな不公平”を、冷静かつ緻密に描き出した社会学の一冊です。
キーワードは「社会移動」。
つまり、「人は生まれた環境から、どれだけ自由に上へ行けるのか?」という問い。
この本は、格差を“数字”や“意見”ではなく、データとリアルな人間の物語で語ります。
読めば、「努力すれば報われる」という言葉の裏にある構造が、少しずつ見えてきます。
■ 「社会のはしご」は、本当に誰にでも開かれているのか
『移動と階級 格差 移動』の中心テーマは、「社会移動(social mobility)」です。
社会移動とは、
- 貧しい家庭から豊かな層へと上がる「上方移動」
- 豊かな家庭から貧困層へと落ちる「下方移動」
といった、世代を超えた「社会的位置の変化」を意味します。
日本は長い間、「中流社会」「努力すれば上に行ける国」と言われてきました。
しかし、著者の伊藤さんはデータをもとにその幻想を静かに崩します。
「日本では、親の学歴・職業・収入が、子どもの将来に強く影響している。」
つまり、スタート地点の違いが、人生の可能性を大きく左右してしまう。
“格差社会”という言葉の裏には、「移動しづらい社会」=固定化された構造があるのです。
■ 格差は“能力”ではなく“環境”で再生産される
『移動と階級 』で印象的なのは、格差を「個人の努力不足」とは切り離して分析している点です。
著者は言います。
「格差とは、能力の差ではなく、環境が生み出す差である。」
たとえば、
- 教育格差:学費や地域差によって進学のチャンスが異なる
- 情報格差:家庭環境が進路や職業の“選択肢”を制限する
- 文化資本:本や会話、価値観が無意識に将来を決めていく
これらの要素が、個人の意志よりも強い力で人生を形づくる。
「努力」だけでは届かない現実を、社会学的に丁寧に解き明かしています。
だからこそ本書は、単なる批評ではなく、**社会を“再構築するための視点”**を与えてくれるのです。
■ 「努力論」の先にある、希望のかたち
一見すると重いテーマに見える『移動と階級 格差 移動』ですが、
読後に残るのは“絶望”ではなく“希望”です。
なぜなら、著者は「構造を知ることこそが、自由への第一歩」だと説くからです。
「個人の努力を否定するのではなく、努力が正当に報われる社会をどうつくるか。」
格差を「仕方ない」と諦めるのではなく、
“なぜそうなるのか”を理解することで、社会の仕組みをより良く変えられる。
その姿勢が全編に貫かれています。
教育政策や雇用制度、地域コミュニティなどへの具体的な提言もあり、
社会を動かすための「知識としての社会学」を感じられる内容です。
■ 「見えない壁」を意識することから、共感が生まれる
『移動と階級 格差 移動』のもう一つの魅力は、
“データの裏にある人の感情”に寄り添っていること。
数字では語れない、
- 奨学金を抱えて働く若者
- 地方から都市に出る時の“文化的ギャップ”
- 家族の期待に押しつぶされる学生
そうした現代のリアルを通して、「階級」という言葉に血が通うのです。
この本を読むと、自分とは違う立場の人の“生きづらさ”が少しわかる。
その気づきこそが、格差社会を変えるための最初のステップなのかもしれません。
■ よくある質問に答えます
Q:社会学の専門知識がなくても読めますか?
A:はい。難しい用語は最小限で、身近な例やグラフでわかりやすく解説されています。
Q:どんな人におすすめですか?
A:社会問題や教育、働き方に関心のある方、また“努力では届かない現実”を感じている方に。
Q:希望が持てる内容ですか?
A:はい。問題を冷静に見つめながらも、「変えられる社会」への視点がしっかり提示されています。
■ まとめ:「格差」と「移動」を知ることは、社会をより良くする第一歩
- 日本の社会は「努力が報われにくい構造」に変わりつつある
- 格差は個人の能力ではなく、環境が生む
- 「社会移動」を理解することで、見えない不公平が見えてくる
- 『移動と階級 格差 移動』は、“知ることが希望になる”社会学の入門書
格差を語ることは、誰かを責めることではなく、
「誰もが動ける社会をどうつくるか」を考えること。
この本は、そんな問いを静かに、しかし力強く私たちに投げかけます。
今の日本を理解したい人、そして未来を変えたい人にこそ読んでほしい。
詳しくはこちら→https://amzn.to/3X2c6eS