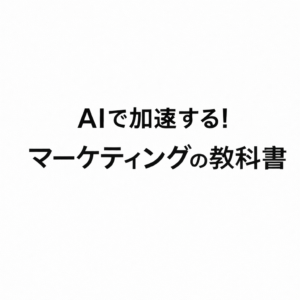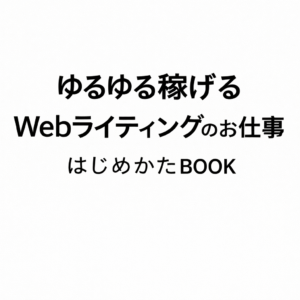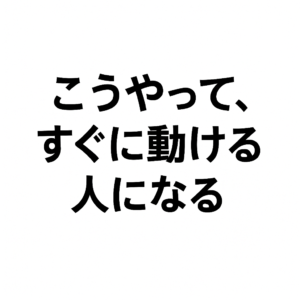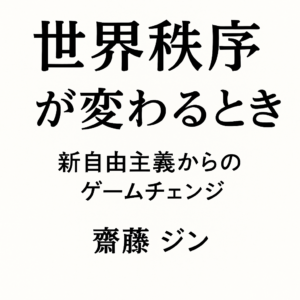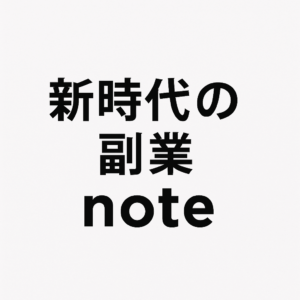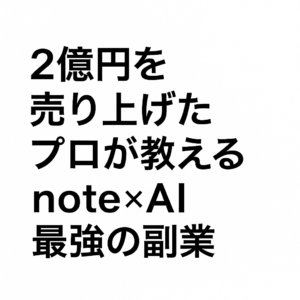「言葉にする前に考える」——『頭のいい人が話す前に考えていること』が教えてくれる、伝える力の本質
「話が伝わらない」「説明が下手だ」と感じたことはありませんか?
同じ内容を話しているのに、なぜか“伝わる人”と“伝わらない人”がいる。
その差は、話すスキルではなく「話す前に何を考えているか」にあります。
安達裕哉さんの『頭のいい人が話す前に考えていること コミュニケーション 話し方』は、まさにその“思考の部分”に光を当てた一冊。
言葉の表面ではなく、「話の構造」「相手との関係性」「目的意識」を整理してから話すことで、どんな場面でも信頼を得られるようになる——そんな本質的なコミュニケーション力を教えてくれます。
■ 「頭のいい人」は、話す前に“3つのこと”を考えている
『頭のいい人が話す前に考えていること コミュニケーション 話し方』では、話す前に意識すべき3つの思考軸が紹介されています。
- 「何を伝えたいのか」——目的を明確にする
- 「なぜそれを話すのか」——相手にとっての価値を考える
- 「どう伝えれば伝わるか」——構成とタイミングを整える
多くの人は「とにかく話そう」としてしまいますが、頭のいい人は話す前に“話す意味”を整理するのです。
つまり、話す力とは「考える力」であり、思考の整理ができている人ほど、少ない言葉で的確に伝えられる。
この考え方は、会議・プレゼン・上司との報告・日常会話まで、あらゆるシーンに通じます。
■ 「伝える」より「伝わる」を意識する
印象的なのは、著者が繰り返し強調する「伝える」と「伝わる」は違う、という言葉です。
話す側がどれだけ丁寧に説明しても、相手が理解できなければ意味がありません。
安達さんは、「伝わる」ために必要なのは**“相手目線の構造化”**だと説きます。
たとえば、
- 抽象的な話をするときは「具体例」を添える
- 自分の意見より先に「背景」や「前提」を伝える
- 聞き手が“何を知りたいか”を予測して構成を組む
この「話の設計図づくり」こそが、“頭のいい話し方”の正体です。
本書を読むと、「話す=即興」ではなく、「準備された思考のアウトプット」だと気づかされます。
■ ビジネスでも日常でも使える「思考の型」
『頭のいい人が話す前に考えていること コミュニケーション 話し方』の魅力は、抽象論で終わらず、誰でも使える「思考の型」が紹介されている点です。
たとえば——
- PREP法(結論→理由→具体例→再結論)で論理的に話す
- ピラミッド構造で主張と根拠を整理
- 相手の“前提”を確かめる質問を挟む
こうしたフレームワークを活用することで、会話が驚くほどスムーズになります。
特に、上司や取引先への報告・相談の際、「話が分かりやすい人」として信頼を得るきっかけになるはずです。
■ 「話し方」ではなく「考え方」を変える
多くの話し方本が「声のトーン」「姿勢」「言葉遣い」にフォーカスする中で、本書は徹底して“思考”に焦点を当てています。
安達さんが伝えたいのは、
「頭のいい人は、話す前に“相手の理解プロセス”を考えている」
ということ。
つまり、相手がどう受け取るかを想像してから話す。
その姿勢が、誤解のない信頼関係を生み出します。
「話す前に考える」というたった一つの習慣が、職場の空気も人間関係も変えてしまう。
この本を読むと、言葉の力よりも「思考の力」にこそ、本当のコミュニケーション能力が宿ることが分かります。
■ よくある質問に答えます
Q:話すのが苦手でも効果がありますか?
A:あります。むしろ「話すのが苦手」な人ほど、“考える”を意識するだけで大きく変わります。会話がスムーズになり、緊張もしにくくなります。
Q:ビジネス書っぽい内容ですか?
A:ビジネスだけでなく、家庭・友人関係など“人と話すすべての場面”で使える内容です。
Q:実践的ですか?
A:とても実践的です。1章ごとに具体例があり、「今日から試せる」思考法が詰まっています。
■ まとめ:考える力が、話す力を変える
- 「話す力」は、「考える力」から生まれる
- 頭のいい人は、“話す前に考えている”
- 相手に合わせた「構造化」が、伝わる話を作る
- 『頭のいい人が話す前に考えていること コミュニケーション 話し方』は、“思考と言葉をつなぐ”一冊
言葉は、考えの延長線上にある。
この本は、ただ話すための指南書ではなく、“より深く考え、より良く伝える”ための哲学書のようです。
あなたの会話が変われば、人間関係も変わる。
詳しくはこちら→https://amzn.to/43BPw0e