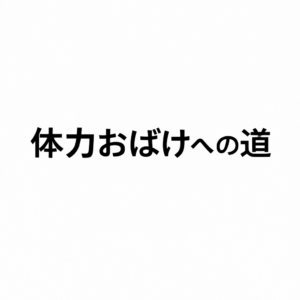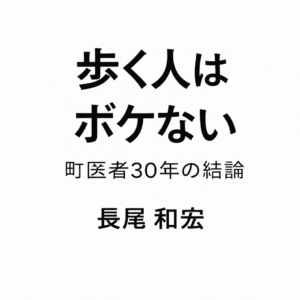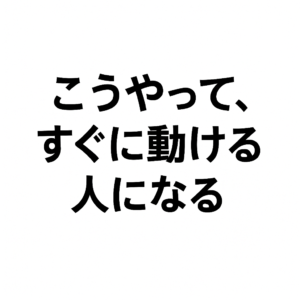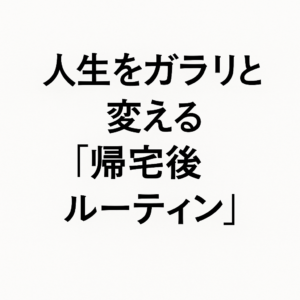「正しい決断が家族を救う」──認知症介護の“迷い”を減らすための現実的で温かい一冊
認知症の介護は、迷いの連続です。
「これで合っているのかな」
「もっといい方法があったのかもしれない」
「私の判断が間違っていたらどうしよう」
そんな“正しさの不安”の中で、
介護者自身が追い詰められてしまうことは少なくありません。
『認知症は決断が10割』 は、現場の最前線で多くの家族を支えてきた
医師・長谷川嘉哉さんだからこそ語れる
“介護の本質は、専門知識ではなく〈決断〉である”
という深いメッセージを伝えてくれる一冊です。
認知症 決断 介護
この3つのキーワードがそのまま、本書が届けたいテーマを象徴しています。
詳しくはこちら→https://amzn.to/4nZRU8z
認知症介護の分岐点は、専門的な判断ではなく「生活レベルの決断」
本書が示す“決断の重要性”とは、
何か専門的な治療選択ではありません。
むしろ、介護者が日々向き合う
生活の中の小さな選択が
本人の症状にも、家族の心の余裕にも大きく影響するという考え方です。
たとえば──
- どこまで自宅で介護するか
- どのタイミングで医療や施設を頼るか
- 本人の「できる」を残すのか、無理を減らすのか
- 介護者の負担をどのラインで減らすか
- 家族内の役割をどう整えるか
これらは、正解がありません。
だからこそ、本書は“状況に合った最善の選択”をするための
思考の軸を丁寧に示してくれます。
「自宅介護」か「施設介護」か──その迷いに答えをくれる視点
介護者誰もが一度は悩む「施設に預けること」への罪悪感。
長谷川さんは、この問いに対してとても温かい答えを示します。
「介護の選択とは、家族全員が幸せでいられる形を選ぶこと」
つまり、
- 自宅にこだわる必要はない
- 介護者の負担は確実に判断力を奪う
- プロに任せることは“逃げ”ではなく“生活の仕組みづくり”
- 家族が笑顔でいられる介護こそ正解
という視点です。
読みながら、
“介護は一人で抱えるものではない”
という安心感がじんわり広がります。
介護を“つらいだけの時間”にしないための、実践的でやさしい知恵
本書には、今日から使える「介護の整え方」が多数紹介されています。
特に印象的なポイントはこちら。
- 本人の“できること”は奪わない
小さな成功が自信と穏やかさにつながる。 - 介護者が疲れれば、家族関係は必ず壊れる
だから休むことこそ“最重要のケア”。 - 医療・介護サービスは早く使うほど効果が大きい
限界まで我慢しない。 - 認知症は“本人の世界”で生きていると理解する
訂正より共感が心を守る。 - 家族全員が“同じ情報の地図”を持つことが大切
意見が割れるのは、情報が不平等だから。
どれも、現場経験から生まれた“リアルで実践的な知恵”です。
「介護は、決断で救われる」という希望
認知症という病気は、変化を避けられません。
だからこそ、
状況が変わるたびに「どうするか」を選び直す力
が介護を大きく左右します。
本書の大きな救いは、
「あなたの決断で、介護はもっと楽になる」
という前向きなメッセージ。
不安や罪悪感の中にいる介護者に、
そっと寄り添い、
「大丈夫ですよ」と言ってくれるような本です。
読後に残る余韻
『認知症は決断が10割』は、
認知症介護を“孤独な戦い”から
“家族でつくる生活”へと変えてくれる本です。
決断に迷うのは当たり前。
正しさはひとつじゃない。
状況に合わせて楽にしていい。
介護をつらさだけで終わらせず、
家族の未来を守るための“考え方”が手に入る本です。
詳しくはこちら→https://amzn.to/4nZRU8z