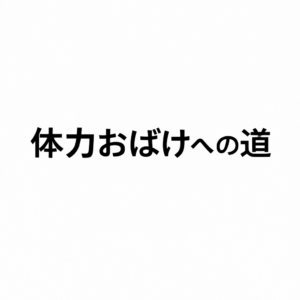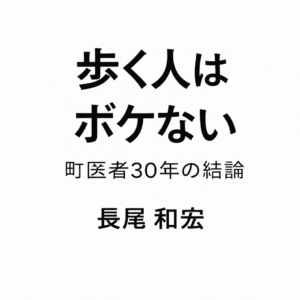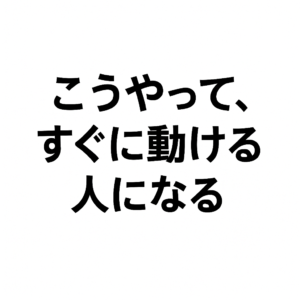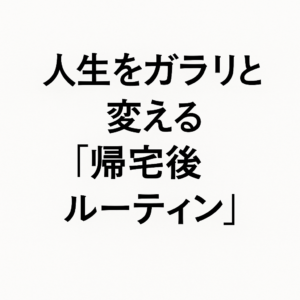「認知症は“奪う病”ではなく、“生きている人”と向き合う時間」
専門医本人が認知症になって初めて見えた“心の奥”に触れる
認知症は、多くの人がどこかで向き合うテーマです。
家族、職場、自分自身の未来。
でも、正しい知識よりも、
「怖い」「不安」「どう接したらいいのかわからない」
という感情のほうが先に立ってしまう──。
そんな日本人の“心の壁”を静かにほどいてくれるのが、
『ボクはやっと認知症のことがわかった』 です。
認知症専門医として多くの患者と向き合い続けた長谷川和夫さん。
その本人が認知症となり、「当事者」としての思いを綴る。
この事実だけでも胸に迫るものがありますが、
本書はそれを“読者のやさしさ”へと変えてくれます。
ボクはやっと認知症のことがわかった 認知症 日本人
この3つのキーワードが、そのまま本の核心を表しています。
詳しくはこちら→https://amzn.to/47KdVDt
専門医としての視点と、当事者としての心。その両方が語る「本当の認知症」
長谷川さんは本書の中で、
専門家としての知識と、当事者としての実感はまったく違う
と率直に語ります。
たとえば──
- 認知症の人は“混乱している”のではなく、“必死に理解しようとしている”
- 怒っているように見えるときは、“分かってほしい”のサイン
- できなくなることは増えるけれど、“感じる心”は最後まで残る
- 周囲の対応ひとつで、症状が軽くも、重くもなる
こうした言葉には、
医師でも患者でもあるという唯一無二の立場だからこそ伝えられる重みがあります。
読み進めるほど、
“認知症を理解する”とは、医学ではなく“心”の話なのだと気づきます。
「どう接するか」は難しくない
必要なのは“正しい知識”ではなく“寄り添う姿勢”
本書に書かれている接し方の多くは、
特別な技術などではありません。
- ゆっくり話す
- 相手の世界に合わせる
- できないことより、できることを一緒に喜ぶ
- 否定しない
- 感情を優先して受け止める
これらはすべて、
“人として向き合う”という当たり前のこと。
ただ、困惑する場面が多いからこそ、
その当たり前が難しくなる。
だからこそ長谷川さんは、
「一番つらいのは“自分でも自分がわからなくなること”」
と伝えたうえで、
まっすぐにこう語ります。
「寄り添ってくれる人がひとりいれば、認知症でも安心して生きられる」
その言葉に、優しさがじんわりと広がります。
認知症は“希望を失う病”ではない
本人の人生は続き、尊厳も続いている
本書の中でも特に心に残るのが、
長谷川さんが語る“希望”についての言葉です。
- 認知症になっても、今を楽しむ力は残っている
- 家族の声や表情は、曖昧でも確かに届いている
- できることは必ずある
- 本人なりの“ペース”が尊重されれば、穏やかな日々は守れる
ここには、
医者として多くを見てきた人の視点だけではなく、
当事者としての“生きる実感”が込められています。
“認知症=終わり”ではない。
むしろここから、新しい関わり方が始まる。
本書はその気づきを静かに、でも深く教えてくれます。
読後に残る余韻
『ボクはやっと認知症のことがわかった』は、
認知症についての本でありながら、
実は“人間の尊厳”と“優しさ”についての本でもあります。
怖さは知識で減り、不安は理解で消え、
関わりはやさしさで変わる。
認知症を知ることは、
家族の未来と、自分自身の未来に希望を持つこと。
理解することは、愛すること。
寄り添うことは、支えること。
そんな温かい気持ちが胸に残る一冊です。
詳しくはこちら→https://amzn.to/47KdVDt