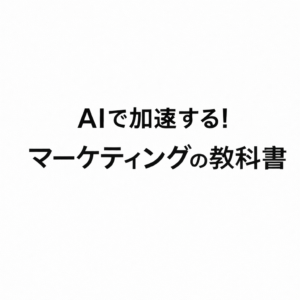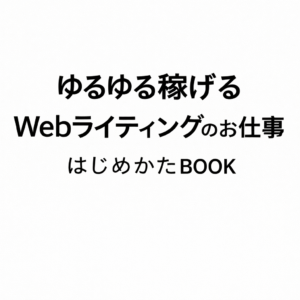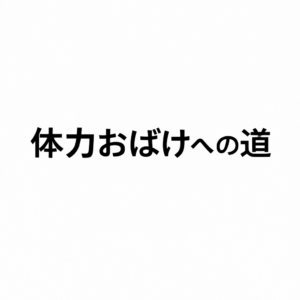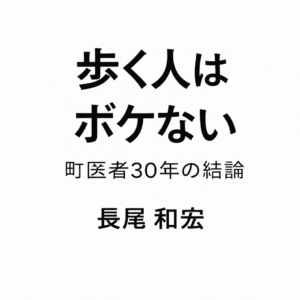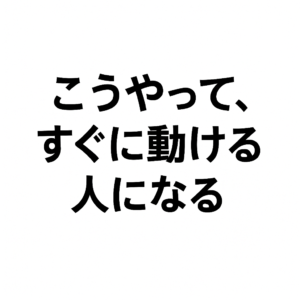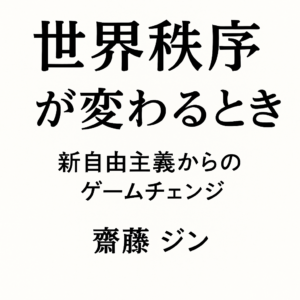“考える”をあきらめない。『こうやって頭のなかを言語化する。』が教える、思考を整えるための言葉の使い方
📖 目次
- 「言葉にならないモヤモヤ」を抱えていませんか?
- 『こうやって頭のなかを言語化する。』が教える“思考整理”の技術
- 荒木俊哉さんが提案する、言葉で自分を整える習慣
- この本から得られる5つの気づき
- よくある疑問Q&A
- まとめ
「言葉にならないモヤモヤ」を抱えていませんか?
「考えているのに、うまく説明できない」
「やりたいことはあるけど、整理できない」
そんな“頭の中の渋滞”を抱える人にこそ読んでほしいのが、
荒木俊哉さんの『こうやって頭のなかを言語化する。』です。
タイトルの「頭のなかを言語化する 思考整理」という言葉の通り、
本書は“考える力を取り戻す”ための実践的な思考トレーニング本。
情報が溢れる時代に、“自分の言葉で考える”ことの大切さを教えてくれます。
『こうやって頭のなかを言語化する。』が教える“思考整理”の技術
荒木さんは、「言語化とは、自分を知る作業」だと語ります。
つまり、話すためでも、書くためでもなく、“自分を理解するため”のツールなのです。
本書では、ビジネスや日常に使える「言葉の棚卸し」や「構造化思考」をわかりやすく紹介。
たとえば、
- 思考を3段階に分けて整理する「フレームワーク思考」
- モヤモヤを紙に書き出して“見える化”する技法
- 感情を客観視し、冷静に判断する“言葉の鏡”の作り方
など、心理学とロジカルシンキングを融合させたメソッドが満載です。
『頭のなかを言語化する 思考整理』は、自己啓発よりも“思考のメンテナンス”に近い内容。
読みながら、自分の中の小さな「言葉の欠片」をひとつずつ拾い上げていくような感覚になります。
荒木俊哉さんが提案する、言葉で自分を整える習慣
特に印象的なのは、荒木さんの“優しいロジック”。
彼は「思考力は、訓練すれば誰でも磨ける」と断言します。
「うまく言葉にできないのは、頭が悪いからではない。整理の順番を知らないだけ。」
この一文に、どれだけの人が救われるでしょうか。
『こうやって頭のなかを言語化する。』では、
“情報を減らすこと”“感情を一歩引いて眺めること”など、
誰でもすぐに取り入れられる具体的なステップを紹介しています。
頭を“整理する快感”を知ることで、
焦りや不安が少しずつ言葉に変わり、
やがて“行動のエネルギー”へと変わっていく。
そんな変化を自然に促してくれる一冊です。
この本から得られる5つの気づき
- 言葉にできないのは、考えが浅いのではなく整理されていないだけ。
- 言語化とは、自分の「今」を可視化する作業。
- 思考を紙に出すだけで、脳の負荷は軽くなる。
- 感情と論理を分けて考えると、判断がクリアになる。
- “言葉で整える”ことが、最高のストレスケア。
『頭のなかを言語化する 思考整理』は、
自分の中のノイズを静め、必要な声だけを拾う方法を教えてくれます。
よくある疑問Q&A
Q1:難しい専門書ですか?
→ いいえ。図解と事例が多く、思考整理が苦手な人ほど読みやすい構成です。
Q2:ビジネス向けですか?
→ 仕事だけでなく、恋愛・人間関係・自己理解にも役立ちます。
Q3:何度も読み返す価値は?
→ あります。読むたびに“今の自分の課題”が変わり、発見が増えます。
まとめ
- 言語化は、自分を理解するための技術。
- 頭を整理するだけで、感情も整う。
- 書く・話す前に、「考える構造」を身につけよう。
- 『こうやって頭のなかを言語化する。』は、思考をクリアにする“脳の整頓本”。
「うまく言葉にできない」そのモヤモヤこそ、伸びしろ。
荒木俊哉さんの言葉は、
焦る現代人の思考を静かに整えてくれる“知的なカウンセリング”のようです。
詳しくはこちら→https://amzn.to/4hHRthG